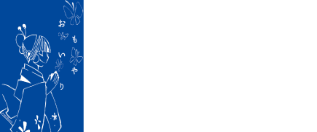本像寺の由緒
本像寺は、具足山と号し、応長辛亥元年(1311)の建立。開基は、勅賜法華宗号の創祖・日像菩薩であります。
宗祖・日蓮聖人から京都弘通の遺命を受けて不惜身命の布教を続けられていた孫弟子の日像上人は、御年44歳の春、洛外擯出を許され、17年ぶりに師の日朗尊者を訪ね、母君の墓所に詣でる東下の行を企てられました。

比叡山の横川を通って宗祖ご留学の遺跡を拝し、堅田から水路をへて木の浜に出られた。たまたま船中で今浜の庄屋今江彦左衛門が上人の教化に服し、上人のために庵を建立した。(これが今の法華寺であります)
このあと東海道を下って身延山に参篭しようと上人は今浜から守山へと進まれましたが、その夜、夢の中に威徳の老翁が現れて「我は正法守護の善神若珍大明神なり。深く正法を慕うて師を待つこと久し。願わくばここに留まってしばらく法を説きたまえ」と告げました。

そこで上人は、比叡山延暦寺の東の支院である東門院の傍の清水町に小庵をかまえて、夜は若珍大明神に法味を捧げ、朝には往来の人々に本化の大法を獅々吼されました。日ならずして熱心な信徒ができたので、本尊を授け、石工に宝塔を刻ませました。これは寺宝として現在に伝えられております。

これが本像寺の起こりで、今浜の法華寺、岩倉の妙感寺と共に近江三具足の霊地として広くその名を知られています。

その後、第5世の日圓律師の代に故あって現地に移転、今日に至っています。歴代上人には学僧が多く宗門の人材養成の道場としても栄えました。