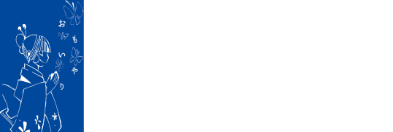本 堂
第5世日圓上人が現在地に移転した際(文明年間)に今浜から移築したもので、18世日成上人の代の元禄4年(1691年)に改築。
享保18年(1733年)21世 日遶上人が瓦葺に葺き替えた。
そして安政4年(1857年)、当時中興の40世日量上人が再度本堂修復を手がけ、旧本堂に至りました。
平成14年に「立教開宗750年・当山開創700年慶讃事業」として現在の本堂が建立されました。
開 山 堂
平成14年に「立教開宗750年・当山開創700年 慶讃事業」として、現在の開山堂が建立されました。
客殿(本像寺会館)
旧客殿は16世日言承認代に建てられたもの。
老朽化したため、開山日像菩薩 第650遠忌記念事業として、旧来の地に、”建物”としては風格のある客殿 「龍華殿」が、その”機能”としては「本像寺会館」が、昭和63年5月に竣工。
同信の集会所、憩いの場でもあり、修養道場でもあり、各種の稽古場、冠婚葬祭 の式場といった多機能、多目的に活用できるものであります。
書院・池庭
書院はかつては客殿内に上段の間としてあり、大名の間として使われるなど格式の高いものでしたが、老朽化がはげしいため昭和37年の開創650年記念の客殿改修の際にとりこわされました。
開山日像菩薩第650遠忌記念事業として池庭の東側に別棟で新築され、昭和60年11月に竣工。
池庭は江戸末期の築庭。開山日像菩薩650遠忌の際、新たにお滝が設けられました。
守護神堂
最初の堂宇は安政3年(1856年)日量上人によって建立されましたが、老朽化したため、 昭和52年に宗祖700遠忌記念事業として再建。 若珍大明神をはじめ、顕明龍神、八将 大金神、八大龍王、稲荷大明神、法力大明神が合祀されています
鐘 楼
初代の梵鐘は寛文11年(1671年)の鋳造。 傷みのため元文3年(1738年) 改鋳。 この時に本像寺の由来などが詳しく彫り込まれたが、先の第二次世界大戦末期に供出。 現在は3代目の鐘が時を告げている。

山 門
江戸時代の文久2年(1862年)中興日量上人によって建立された格調高い高麗門で、瓦の装飾は見事だが、何度も改修の手をへて往時の面影はうすれていましたが、平成●●年、宗祖降誕800年慶讃事業として